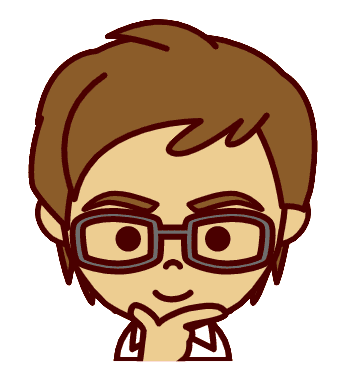今回は、逆上がりのコツは鉄棒好きになること。テクニックより先に精神論!というテーマで書いていきます。

4歳の我が子が最近幼稚園で鉄棒の練習を始めたらしい。前まわりはできたけど、逆上がりがなかなかできないと悩んでいるので、公園で練習に付き合いました。でもすぐ飽きちゃって上手くなる気がしません。こんな我が子ですがどうしたら逆上がりができるようになりますか?
逆上がりって大人でもできない人がいるくらい、意外と難易度高いんですよね。でも一回できるようになるととても自信がつく技なので、是非親としては、幼児期の成功体験の一つとして、逆上がりができるようにしてあげたいものです。
でも教えるのって結構大変。筋力の問題なのか、テクニックの問題なのか、見ただけですぐわかればいいですが判断が難しいんです。
我が家の体験談としては、長女が逆上がりの練習を始めて1カ月半くらいで逆上がりができるようになったので、このようなお悩みを解消する方法を、実体験を交えて書いていきたいと思います。

我が家は3人の子供がいて、あまり公園に連れていく時間が取れないので、自宅に室内用鉄棒を買って毎日練習をしました。
逆上がりのコツ【テクニック論より精神論】
逆上がりが出来るようになるコツや教え方のコツは世の中たくさんの人が答えていますが、実際我が子に教えてみて意外と一番大切だと感じたのが気持ちの部分です。
鉄棒から落ちたら痛そう
回るの怖い、頭打ったらどうしよう
逆上がりって難しい
友達はできて私はできない
こんな気持ちがある状態ではそもそも練習するのも嫌ですよね。
でも、逆上がりくらいまでは練習すればできるようになります。コツ云々知らなくても何度もチャレンジすればできるようになる。
要するに、鉄棒を好きになって自信を持てれば、少し教えてあげれば子供自信の力で逆上がりは出来るようになります。
もちろん練習意欲が出てきたらコツを伝授することも大切なので、後半ではテクニックについて触れていきます。
逆上がりのコツ【一番大事なのは鉄棒を好きになること】
まずは鉄棒に対する苦手意識をなくすことが先決。何事も「好きこそものの上手なれ」です。嫌々練習していては、できるものもできません。
ということで、鉄棒を好きになるためにという部分を解説していきます。
まずは、
豚の丸焼き
前まわり
など簡単な技をやっていきましょう。
「豚の丸焼き」もできない状態であれば、両手でぶら下がって前後に揺らして「ブランコ」ができたら、まずはそれでも十分。
技と呼べないくらい簡単な技でも、できたら徹底的に褒めてあげる。これで、子供は鉄棒が好きになり、しばらく鉄棒から離れなくなります。

我が子の場合はその後、「パパ、見て見て~!」が続き、しばらくは得意げに「豚の丸焼き」を見せてきては褒める、ということを続けてみました。
逆上がりのコツ【鉄棒から落ちたら怖い、回るのが怖いを緩和してあげる】
簡単な技をやりながらも、触らないくらいの距離で支えてあげましょう。
ここで万が一手を離して頭を打ってしまうと鉄棒への恐怖が植え付けられますので、万が一のために近くで見守りつつ、いつでもガードできるように準備が大切です。
特に公園などの外で練習する場合は注意が必要です。

我が家は室内用鉄棒を買ったので、畳の上に鉄棒を置き、下に布団を敷いて遊んでいます。
逆上がりのコツ【シンプルにお尻を上にあげるだけ】
逆上がりは難しい技ではないということを教えてあげましょう。実際にお尻を押して逆上がりをさせ、足の付け根を鉄棒に乗せるところまで補助してあげます。
※その後、自力で着地までいけなければ、足を下に押してあげれば逆上がりができることを教えます。
そう、重要なのは、前半の「足の付け根を鉄棒にかけるところ」だけ。ここまで自分で持ってこれるようにすればいいんです。そのやり方だけ、テクニックでカバーをしていきます。
逆上がりのコツ【テクニック系の話】
ボクなりの逆上がりのコツはこの4つでした。
足は真上に蹴り上げる
蹴り上げた瞬間は真上を向く(上体を倒す)
体を鉄棒から離さない(腕を曲げたままに)
膝(ひざ)は曲げない
これを更に噛み砕くと、こんな感じです。
足の動き
始めは足をチョキに、後ろ足を前に振り上げる視線の動き
始めは斜め上を、蹴り上げたら真上を見る肘の動き
鉄棒に近づき、終始腕を曲げたまま回る

このポイントで教えると割とすぐ逆上がりができるようになると思います。個人差がありますが、我が子の場合は家で毎日練習して、1カ月半かかりました。
少しボクなりの解釈で解説しましたが、参考にしたyoutube動画がこちらです。
まとめ
ということで、逆上がりのコツについてテクニック論よりも精神論が大事ということで、体験談をもとに書いてきました。
それでは、読者さんのお子さんの逆上がりが上達することを願っております。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。