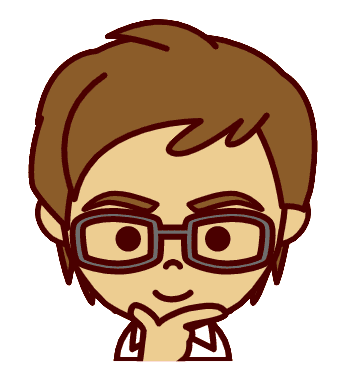今回は、子供が寝ないとお悩みのママさんへ、3人育児で毎日7時就寝の我が家の5つの習慣をご紹介します。

最近体力がついてきた3歳の我が子が夜なかなか寝てくれない。子供はたくさん睡眠を取らないと発育に良くないと聞くからなんとかしたいけど、どうすれば早い時間に寝てくれるんだろう?
2〜3歳の理想の睡眠時間は12時間くらい。こういう情報を知ってしまうと、我が子の睡眠時間と比べ、心配になりますよね。
それに加え、子供が寝た後の時間が自分の趣味時間というママさんも多いのはず。
そんなこんなで、我が子にできるだけ早い時間に寝てほしいと思うのは当然だと思います。

我が家は毎日7時前に起床、20時には全員寝ついているという生活を送っています。早寝早起きを実現するために妻が実行している5つの習慣をご紹介します。
妻は専業主婦ですが、ワーキングママでも取り入れられることがありますよ。
寝る時間を早めるためにはリズムを作ることが大切
早寝を実現させるためには、早い時間に寝る習慣(生活リズム)を作ること。実はこれが全てです。
WEB上には早寝のためのコツ・TIPSみたいな情報が溢れていますが、ボクはシンプルにこれに尽きると思っています。
なぜなら、大人にも言えることですが、だいたい眠くなる時間って毎日一緒ですよね。
やることがなくて暇を持て余してるから今日は早く寝ようかなと思っても、なんだかんだスマホやTVを見てしまい結果なかなか寝れなかったり。
子供も一緒で、その日の疲れ具合にもよりますが、毎日同じくらいに目が覚めて眠くなる。そういうものです。
つまり、寝る時間が遅くなる子は、その時間に眠くなる習慣が身についているということなので、早寝の習慣に変えていく必要があるんです。
それでは、早寝の習慣をつけるために我が家が気をつけていることをご紹介していきます。
休みの日でも朝7時には家族みんなでそろって起床
朝は仕事や幼稚園が休みの日でも6:30に目覚ましをかけ、みんな一緒に7時には起床。朝は早起きの習慣をつけるようにしています。
習慣化のためには、「みんな一緒に」という部分が重要で、大人がだらだらしていると子供も真似るもの。大変だけど親が背中を見せる必要があります。
朝起きるのが遅くなる
昼寝から起きるのが遅くなる
夜眠くなるのが遅くなる
また朝起きるのが遅くなる
まずはこういった悪いサイクルを頑張って断ち切ることです。

正直、ボクは夜型人間だったので、この習慣を始めてしばらくは修行のようで、とってもつらかったです。
ご飯は3食しっかり食べる
ご飯はしっかり食べること。特にお昼ご飯をしっかり食べることでスムーズなお昼寝にもつながります。
食事の時間も平日休日問わず、時間を大きく前後させないようにすると、お腹の時計もきっちり整うので体内時計の正常化につながります。
お風呂は毎日湯船でしっかり温まる
我が家は夏でも冬でも湯船に入るようにしています。お風呂で温まることで自律神経が整い入眠しやすくなります。
それから、お風呂はだいたいどの家庭も夕飯の前後だと思いますが、家庭によってやりやすい順番が違うと思います。イレギュラーを作らず一定の順番で流れを作ると子供も覚えやすいです。

我が家は、お風呂→夕飯→歯磨き→寝室の流れで、お風呂工程に差し掛かると1日の締め括り。今日も終わったなぁというイメージです。
寝室に入ったら電気はつけない
子供はどうしても明るいと遊び始めてしまうので常夜灯や足元灯などは一切つけないようにしています。これも癖がつくと、明るくないと寝られなくなってしまうので注意が必要です。
ちなみに冬は暗いので、ママが布団に入るとママを囲むように子供たちがくっついてきて、軽くお話ししていると30分以内には順次寝息に変わってきますが、
夏は7時頃はまだ若干明るいので、30分くらい早めに寝室に行き、布団の上で姉妹でキャーキャー遊んでるうちに眠くなるという感じです。
早く寝て!と思わないようにする
寝かしつけた後、やらないといけないことがあったりすると、早く寝てくれと思うこともありますよね。
でもそういう時こそ、子供は寝なかったりするんです。こういうのって伝わってしまうので、流れに任せることにしています。
逆に、早寝のために意識していないこと
寝る直前はテレビを見せない
たくさん運動させる
適切な室温の調節
昼寝の時間調節
これらはよく、寝かしつけを早めるために必要だと言われますが、我が家は意識していなくても早寝できています。
ということから、これらは一時的な早寝には繋がるかもしれませんが、長い目で見たときに本質的に効果があるのかは疑問かなと。
つまり、これらのテクニック的な部分に頼るのではなく、自然と眠くなる時間を前倒しできるように習慣づけていくことが最重要ですよ。
まとめ
ということで、なかなか寝ない子の習慣を変えるための5つのポイントについて、体験談をもとに書いてきました。
それでは、今回ご紹介した5つの習慣を1つでも取り入れて、読者さんの家庭でもお子さんの就寝時間が少しでも早まることを願っております。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。